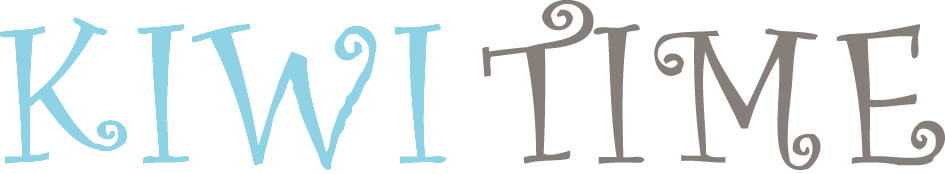夏芽からの返信は、意外なほどに早かった。
砂時計の砂が落ちるのを見届け、店に鍵をかけて自宅のキッチンに入ろうとしたとき、メッセージの着信を知らせる音が、ポケットの中から静かに届いた。
《あら、愛らしい!大きさも、使いやすそう。傷はないの?》
さっぱりとした短い文章だけれど、話し言葉がそのまま文字になったメッセージから、大島の脳裏には、高校生の頃の夏芽がありありと蘇った。嬉しいときには幼な子のようにはしゃぎ、何かを期待しているときは大島の瞳を覗き込んでいたずらっぽい表情を見せる。それから、心配事があるときには、何故かやや唇を尖らせるから、機嫌が悪いようにも見える。そして、知りたいことがあるときには、徹底的にまっすぐな視線を向け、揺るがない。
クルクルと変わるその表情から、いつの間にか、心地よさと命の息吹のようなエネルギーをもらっていたことに気づいたとき、大島は、少なからずうろたえた。相手は、担任するクラスの生徒である。教員の職に就いてから、生徒との間にそのような波長が生まれたことなど、一度もなかった。誤解を恐れずに言えば、大島は、女子生徒から人気があることは自覚していた。しかし、自分の心が動くことなど、彼女たちからひとりの男として影響を受けることなど、一切なかったのである。
だから、赴任して最初の夏休みが終わった後、夏芽が親しく話しかけてくるようになっても、最初はこれといって気にしたわけではない。しかし、冬休みが近づく頃には、大島は、自分の左手の薬指に収まっている結婚指輪が、妙に気になるようになっていた。
《俺も、久しぶりに手に取ったけど、これは、やっぱりいいな。傷は、ほとんどないよ》
大島は、キッチンのドアにかけた手を引き、押し入れのある客間へと向かって、昨日見つけた木製の猫の置物を再び手にする。背中部分に、数センチ程度の短い傷があるので、それを写真に撮って、メッセージに添えた。
《状態も、いいね。それにやっぱり、先生らしい優しくて愛嬌のある雰囲気!近いうちに、実際に見に行かせてください》
その返事に、《ぜひ見に来てください》と敬語で返したのは、夏芽の言葉が社交辞令かもしれないと感じたからだ。
しかし数日後、夏芽は本当にやって来た。
何もかもを柔らかく透明な空気で包み込むような、無邪気が空気中に散りばめられているような、春の昼下がり、「先生」と声を弾ませて、彼女は大島の店のドアを開けた。