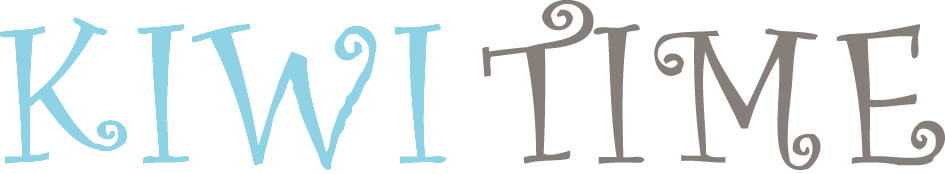「おぉ、来たか」
押し入れの奥から出てきた猫の置物を写真に撮って送り、それに対して夏芽から「近いうちに見に行く」と返事があったときには、半分は社交辞令ではないかと思っていた。しかし、半分は実際に来るかもしれないと期待していた。
店を訪れた夏芽に向けた顔と言葉には、社交辞令ではなかったという驚きと、期待が実現した嬉しさと、どちらが出ていただろうか…と、咄嗟に大島は、一瞬前の自分の顔と声を思い出そうとしていた。
「連絡しないで来ちゃったけど、よかったかな?」
ダメだという返事など、まるで想定していない夏芽に、大島は「おぅ」と言った後にあえて目を合わせて笑った。そうすることで、動揺が隠れるような気がした。
あの猫の置物は、まだ店には出していないことを告げると、「ちょっと待ってて」と大島は店の奥のドアから自宅に入る。ダイニングの横を通りかかったとき、テーブルの上にある知人からもらったクッキーが目に入った。そういえば、クッキーは夏芽の好物であったことを、大島は思い出す。夏芽の高校時代、二人でよく食べた。職員室には、多くの教員や生徒が出入りするが、大島の担当科目であった国語の教材室は、ほとんど人が入らない。そこで、放課後によく、ひとつのマグカップと数枚のクッキーを挟んで話をした。おかげで、甘い物を好まなかった大島も、クッキーだけは好きになってしまった。
「夏芽、今もクッキー好きか?」
コーヒーとクッキー、それから教材の古い紙の匂いがないまぜになった香りを鼻の奥に思い出しながら、大島は店で待つ夏芽に尋ねる。「もちろん」と笑って頷く彼女に、「食べていくか?」と即座に気軽に促したのは、それが懐かしさと好きなものを食べさせたいという親切心からきた言葉だったからだろう。
閉店後、コーヒーカップを洗いながら、大島は「なんか、懐かしいね」とはにかんでクッキーを口に運ぶ夏芽を、思い出していた。最初は、家に上がることを躊躇していた夏芽だったが、離婚して一人暮らしなのだと告げると、どこか安心したように首を縦に振った。
約束の猫の置物を見せながら、大島がそれを手に入れた頃の思い出話をして。夏芽の最近の仕事の様子を聞き。そして、丁寧に包んだ猫の置物を手渡すと、時空を自由自在に操るような二人の時間は、終わっていった。
「じゃ、また」
別れ際に、お互い同時に口にしたけれど。
じゃ、また、何なのか…は、言葉の外に隠されたままだった。