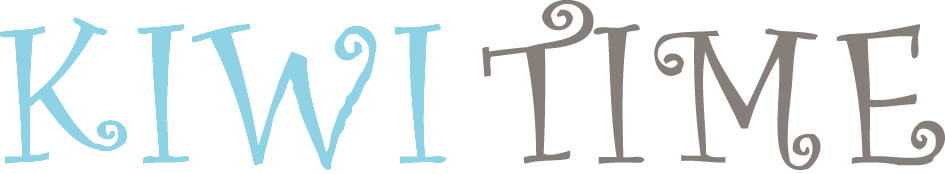リアルな絵とは、本当はこのようなものではないか、「絵を描く」という行為の本質は、こんなところにあるのではないか?と思わせる作品だ。思い出したのが世界史(あるいは美術?)の教科書でもおなじみの「ラスコー洞窟」の壁画だ。両者から感じとられる、原始的要素や素朴さといったありきたりなキーワードでは語り得ない、絵の「本質」とはなんだろうか?
この絵の鑑賞者は知らない間に笑顔になっているのではないか。豚のとぼけた表情、しつこいくらいのうんちの描き込みと臭いの放射線。フェンスの細かい金具に至っては、ファームに住んでいなければ、おそらく描かないものだろう。これらすべてがファームに住むこの画家にとって「リアル」なものであり、鑑賞者はその画家の純粋なまでのリアルな視点に、微笑みながらも「この子はまさにこの環境で生活しているんだ」と納得してしまうのではないか?遠近感が平面的なので、本来浮かないもの(うんち)が宙に浮くという超常現象が起こっているが、ああ、ここではうんちにも飛ぶんだ、と思わせるような説得力がある。この作品もラスコー壁画も、目に映る日常をスケッチする、という点では同じだ。もし、ここに描かれている同じ光景を、商業画家が描いたらどのような作品になるだろうか?うんちは脇役として追いやられ、空と牧草地が中心の、写真のような「いかにも」的作品に仕上がり、「ああ牧場だ」「おお豚がいる」という感想(というより、絵そのものを描写する言葉)しか思い浮かばないのではないか。
記録したい、描きたい、という古代人の思いがひしひしと伝わってくる洞窟絵。そして農場に暮らす少女の眼に映る動物とうんち達。絵の本質…絵は描きたいから描く。眼に見えるものを懸命に描く、楽しんで描く。そして描かれた作品にそれが表れて、観る人にその「リアルさ」が伝わるのだ(と思う)。
この記事は、ニュージーランドの日本語フリーペーパー「KIWI TIME Vol.104(2018年11月号)」に掲載されたものです。