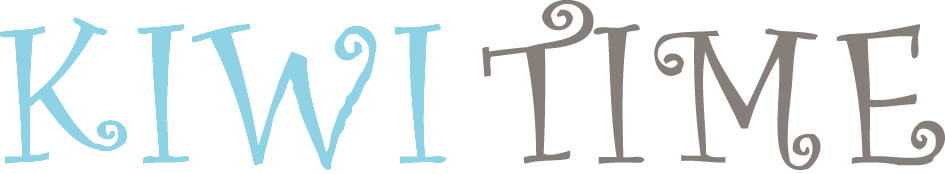塩のつくり方 [SHIO]
現在の日本では、日本の気候・環境に合わせてさまざまな塩づくりが行われています。ここでは、日本のおもな方法2つをご紹介します。
日本発の塩づくり
イオン膜・立釜法:イオン膜を利用して海水から濃い塩水をつくり、その後煮つめて塩の結晶をつくる方法です。
- 海水中の塩分は、ナトリウムなどのプラスのイオンと、塩化物などのマイナスのイオンに分かれて溶けています。
- イオン膜には、のイオンだけを通すものと、のイオンだけを通すものがあります。この2種類の膜を交互に並べて海水を入れ、両側から電気を通すと、のイオンは側に向かい、のイオンは側に向かうので、濃い塩水の部屋とうすい塩水の部屋ができます。
- 濃い塩水から水蒸気の熱で水分を蒸発させて塩の結晶をつくります。
- こうして塩ができます。これを乾燥させてサラサラにしたものが「食塩」です。
天日塩から塩の結晶をつくる
溶解・立釜法:外国から輸入した天日塩を水に溶かして濃い塩水をつくり、その後煮つめて塩の結晶をつくる方法です。
- メキシコなどの塩田でつくられた天日塩を日本に輸入し、水に溶かして砂などの不純物を取り除き、きれいな濃い塩水をつくります。
- 濃い塩水から水蒸気の熱で水分を蒸発させて塩の結晶をつくります。
3. こうして塩ができます。これを乾燥させ、さらに固まるのを防ぐために炭酸マグネシウムを加えたものが「食卓塩」などです。
*立釜:密閉された釜
一方、世界では、岩塩や天日塩を原料とする塩づくりが中心です。
岩塩:岩塩も元は海水
◇岩塩ができるまで
ながいながい年月をかけて海の水が、岩塩になります。
大昔、地殻変動で海の一部が陸地に閉じ込められ、塩分が結晶化し、その上に土砂が堆積してできたと考えられています。形成時期は5億年から200万年前といわれ、世界の塩の生産量の約3分の2が岩塩からつくられています。世界中には数多くの岩塩がとれる場所がありますが、日本にはありません。
◇製品になるまで
掘り出した塩を細かく砕いてつくる方法のほか、地上から水を注ぎ濃い塩水にしてから吸い上げ、その塩水を煮つめてつくる方法があります。
岩塩は不純物を含んでいることが多く、掘り出した塩を一度水に溶かして異物を取り除いてから煮つめることもよくあります。
太陽と風の力で塩づくり
天日塩:
天日塩は、海水を塩田に引込み、太陽熱と風によって水分を蒸発させ塩を結晶させる方法で、自然の力を利用しています。現在の天日塩田の多くは次のような構成となっていて、約2年かけて貯水池から結晶池にむかって海水をゆっくりと流していく方法がとられています。世界ではメキシコやオーストラリアが主要な生産国として知られています。雨が多い日本には、メキシコやオーストラリアのような大規模な天日塩田はありません。
世界の塩生産量の割合をみると、岩塩などを原料とした塩が2 / 3、天日塩など海水を原料とした塩が1 / 3です。
日本では岩塩がとれませんので、日本の塩は、そのほとんどが海水を原料としています。
塩の用途
◇知っていましたか?
これぜんぶ“塩” が使われているんです。
塩は、食用に使われるだけではなく、工業の原材料となったり、雪の日に道路が凍るのを防ぐためなど、わたしたちの暮らしとさまざまな形で関わっています。
味をつける:調味料として味つけに使われます。
脱水・防腐:食品を塩漬けにすると、雑菌が利用できる水分が少なくなり、腐敗の原因となる雑菌の働きがおさえられます。
グルテンの形成:小麦粉に塩水を加えてこねると、パンを膨らませたり、うどんのコシを出したりするグルテンというタンパク質ができやすくなります。
発酵を助ける:食品を腐敗させる雑菌の働きをおさえるため、発酵に必要な微生物が働きやすくなります。
粘り気や弾力を持たせる:魚や肉のタンパク質を水に溶けやすくし、かまぼこやハムなどに粘り気や弾力を持たせます。
医薬用:生理食塩水やリンゲル液などの原料として使われます。
道路の凍結防止:濃い塩水はマイナス20℃くらいまで凍らないため、道路に撒いて路面の凍結を防ぎます。
イオン交換樹脂の再生:ボイラーなどに使われるイオン交換樹脂は繰り返し使用すると性能が低下しますが、塩を使うと性能が元に戻ります
革製品:原料となる皮の保存やなめしに使われます。
家畜用:牛などのエサに混ぜたり、自由になめられるように塩のかたまりを与えたりします。
以下は、塩を原材料としてつくられた各種ソーダ製品の用途です。
ホーロー製品:高温で鉄にガラスを焼きつけるホーロー製品づくりに使われます。
石けん:脂肪などの石けんの原料に混ぜて、石けんをつくります。
パルプ:紙やレーヨンの原料であるパルプをつくるため、木材を溶かすときに使われます。
アルミ製品:アルミのもとをつくるため、原料のボーキサイトという鉱石を溶かすときに使われます。
水道水:水道水の消毒に使われる薬の原料になります。
塩化ビニル製品:石油からできるエチレンと反応させて、塩化ビニル製品の原料になります。
ガラス製品:鉱物のケイ砂や石灰石と一緒に熱してガラスをつくります。
出典:公益財団塩事業センターサイト内「塩百科」(http://www.shiojigyo.com/siohyakka/)

鶏の塩釜焼き[SALT CRUSTED CHICKEN]
大迫力のごちそう料理。
しっとりした塩で包み込んで焼くだけのシンプルな作り方をNOBUさんに伝授していただきました。
材料:
鶏肉 1羽(1kg)
塩 1.5kg
卵白 2個分
黒コショウ適量、調理用の油大さじ1
作り方:
- 鶏肉全体に黒こしょうをふりかける。
2.ボウルに塩を入れて卵白を加え、全体がふわっと、しっとりするまで手でよく混ぜる。
3.フライパンに油を入れて十分に熱したら、鶏肉の背中から焼き、焦げ目ができたら裏も同様に焼く。
4.天板にオーブンシートを敷き、2の塩を1/4を広げ、鶏肉を置いたら残りの塩を鶏肉全体にかぶせるようにのせ、形を整える。
5.あらかじめ温めたオーブンに入れて、200℃のオーブンで40~50分ほど焼く。
6.塩釜に焼き色がついたらオーブンから出し、器に盛りつけて出来上がり。塩釜を包丁で切って鶏肉を取り出したら、余分な塩をはけ等で取り除く。
オマケ:
- 塩加減が十分なので、生野菜(キュウリやトマト、レタスなど)を添える
- お好みでローズマリーや生姜、ニンニクなどを鶏肉に詰める。
- 今回は焼き上がりを包丁で切ったが、めん棒などで叩いて割るのも楽しい
協力:NOBU(@fishing_and_eating)
この記事は、ニュージーランドの日本語フリーペーパー「KIWI TIME Vol.106(2019年1月号)」に掲載されたものです。