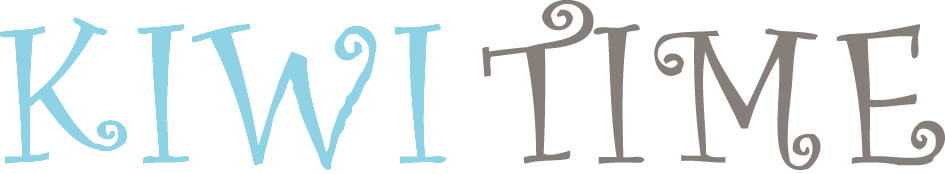![]()
【第3話】
秒針の音に気づいて目を向けると、時計は十時を指している。メル友の募集に、存外、『リカさん』という女性からメールをもらったと気づいたのが、朝の七時。十行にも満たないメールを返信するのに、三時間も費やしたのか…。
苦笑いと微笑の混じった短いため息をつくと、バスルームに向かい、午後に一件入っている仕事の打ち合わせへと頭を切り替えた。
「行ってくるよ」
外出前、妻の写真に手を合わせる。それは、妻が他界したときに十四歳と十一歳だった娘たちと一緒に始めたことで、二人が独立しても、やはり、十年以上をかけて染みついた習慣は抜けない。声をかける前、妻が好きだったチョコレートを一粒、供えることも。そして、帰宅後にそのチョコレートを食べることも。
最初は、娘二人と俺の三人で順番に食べていたから、小さな甘い粒を口に入れるのは、週に二回程度だった。それが、長女が遠方の大学に進学すると一日おきになり、一年ほど前に次女が大学を卒業して家を出てからは、毎日になっている。
写真の中で笑う妻は、やはり、美しい。子宮がんが発覚してわずか半年で、砂漠の水が蒸発するようにいなくなってしまったとき、妻は四十三歳だったが、この写真はその三年ほど前に撮ったものだ。予報に反して青空が広がった春の日曜、「お弁当を持って出かけよう」という妻の突然の提案に、家族で公園に出かけた。冷蔵庫の残り物をとりあえず挟み込んだような、ハムとレタスと卵のサンドイッチを自画自賛しながら、娘たちに負けない勢いで頬張る妻。その笑顔が日光に反射した瞬間、思わずカメラを向けた。それは、俺の職業がカメラマンだからかもしれないし、夫だからかもしれない。
「ただいま」
打ち合わせを終えて帰宅する頃には、日が沈んでいた。妻の写真の前のチョコレートを手に取ると、急遽明日の朝に納品してほしいと頼まれた写真をチェックするために、急いでパソコンを立ち上げる。
白米を要求する胃からの抗議をなだめながら茶色いかたまりを口の中に放り込んだとき、新着メールを知らせるアラームが鳴った。
(そういえば…)
急に立て込んだ仕事に、脳の隅へと押しやられていたが、今朝、俺は『リカさん』にメーをしたのだ。
もしかしたら、返信がきたのかもしれない。突然、胸のあたりがざわめき、急ぎの仕事があることも、空腹であることも、綿毛のように風に飛ばされていった。
口の中では、ダークチョコレートがゆっくりと溶けてゆく。
つづく
ほほか:主に日本向けに、女性の美容健康についてのコラム、女性向け恋愛小説等を執筆するフリーライター。外見の美よりも内面の健康と美しさにフォーカスして、より多くの女性が充実感とともに毎日を生きるサポートとなる文章がテーマ。2002年よりNZ在住。散歩、読書、動物とのたわむれ、ドラマと映画鑑賞が趣味。
◆題字・イラスト◆ はづき:イラスト、詩、カードリーディングを通じて癒しを伝えるヒーラー。すべての人の中に存在する「幸せを感じる力」を、温め育てるヒーリングを目指す。
Instaguram:nzhazuki┃w:malumaluhazuki.com
この記事は、ニュージーランドの日本語フリーペーパー「KIWI TIME Vol.93(2017年12月号)」に掲載されたものです。