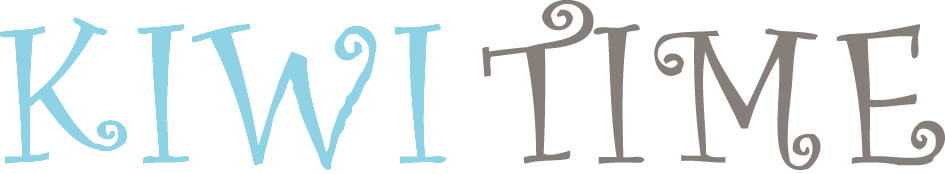夏芽を、店の奥にある自宅に上げて以降、大島は、彼女を待つともなしに待っている自分に、薄々気づいていた。だから、二週間後に連絡が来たときには、随分と長い間、音沙汰がなかったような思いがした。
《今、先生のお店のけっこう近くで買い付け中。こんなの見つけちゃった。先生、好きそうだね》
メッセージに添えられていた写真には、小さなロココ調の布張りの椅子と、それに腰かけたウサギの人形が写っている。
《おぉ、いいな。たまには、いろいろ見て歩きたいな》
そう返信した十分後には二人は待ち合わせることとなり、三十分後には大島は夏芽の車の中にいた。
「なんか、嘘みたい。先生が私の車の助手席にいるなんて」
「そうだな」と返して笑うと、大島は、もう三十年以上前、学校からの帰宅中、部活を終えて駅に向かう夏芽と偶然会い、車に乗せて駅まで送ったときのことを思い出した。後にも先にも、大島の車に夏芽が乗ったのは、そのときだけである。
「あのときは、私が助手席にいたのにね」
小さな沈黙の間に、夏芽も同じ記憶を引き出しているのだと知り、大島の胸には、どうしようもない甘酸っぱさがこみあげてきた。

「やっぱり、先生のダイニングにぴったりだよ、これ」
行きつけの輸入雑貨問屋を二人で何軒か回った後、大島の自宅に戻ると、夏芽は購入したアンティークのグラスをダイニングテーブルに乗せて満足気にそう言ったのである。
「仕事用じゃないのか?」
ダイニングに背を向けて紅茶を淹れていた大島が振り向くと、椅子に腰かけてテーブルに顔を近づけ、間近でグラスを眺める夏芽が目に入った。
好きなものを見つめるときの、奥に玉虫色の光源があるような瞳の輝きは、高校生の頃と変わらない。
「好き…だったんだ」
ティーカップに視線を戻しながら、大島は、思わず言葉にした。
「え?」
夏芽が顔を上げるのが、背中でも分かる。
「あの頃、俺、お前を、本当に好きだったんだ」
「…うん」
「あの頃っていうか…多分、今も」
「…多分?」
夏芽の声が笑みが含んでいたので、大島は、振り返ることができた。
「多分っていうのは、失礼か?」
目を合わせて笑う大島に、夏芽も玉虫色の笑顔を返す。
笑顔からは、少しずつ緊張が消え、代わりに、安堵感が染み渡る。
「私も。あの頃、すごく好きだった。多分、今も」
「多分」と、二人の声と同時に笑顔が再び重なる。
湯気が立つカップをテーブルに並べると、大島は、夏芽の隣に座って彼女の手を取った。