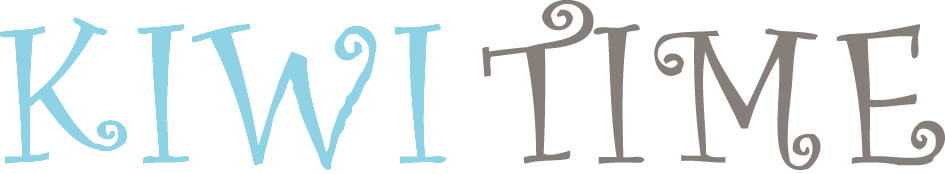重なり合った大島と夏芽の手の上に、二人で買ってきたばかりのアンティークグラスを屈折しながら通り抜けた光が、うっすらと虹色に伸びている。
大島は、夏芽の左手を包んでいる自分の右手の指先に、ほんの少しだけ、力を入れた。夏芽は、手を引かない。すんなりと吸い付くように、大島の掌に自分の手の甲を馴染ませていることに、夏芽自身、気づいていた。大島が、もう一段、指先に柔らかな力を宿すと、夏芽はくるりと手首を返す。掌が重なると、二人は、しばらく、互いの指の存在を丁寧に確かめるように、ゆっくりと撫で合っていた。
数十秒間というその刹那に、三十年以上分の時間の糸を、切れないように絡まないように、重なった手の中にたぐり寄せる。黙って。片方の掌で、互いの鼓動も息づかいも、心から漏れる音も、すべてを感じ合いながら。
大島が、夏芽の指と指の間に自分の指をそっと沈ませると、夏芽はそれに応じて指を広げ、大島の指を引き寄せるように絡ませた。ゴクリと喉が鳴る振動が、繋がれた指にまで響いた気がして、大島は、照れ隠しで指をほどき、その勢いで夏芽を抱き寄せる。
「夢みたい」
さらなる数十秒の間の沈黙を破ったのは、夏芽の、吐息混じりの小さな声だった。大島の胸に素直に頭を預けたまま、「こんなに先生のそばにいるなんて、夢みたい」と、声の大きさも甘さも少し増して、夏芽は続けた。
「俺、お前よりも随分早く、死ぬんだろうな」
声と体の振動との両方で聞こえてくる大島のその言葉は、夏芽には、唐突なものに聞こえた。
「そんなの、分からないじゃない?」
「まぁ、そうだけど」
緊張を少しだけ解いた声で笑いながら、その笑みを含んだままの声で「俺が死んだら、店の商品、お前、売ってくれる?」と大島は問う。
「売るわけないよ。私がぜんぶ、もらっちゃうもん!」
同じだけ笑みを込めた声で夏芽が返した後、「まぁ、それもいいか」と大島が笑うと、二人はまた、しばらく口を閉じた。
「先生…」
抱き寄せる腕に力を込めようとする大島を鋭く制するような、でも震えた声が、夏芽の口から流れる。
「婚約している人がいて。でも、どうしようかなって。やっぱり、やめるかもしれなくて」
大島にも自分自身にも言葉を挟む隙を与えないように、夏芽は、ひと息に喋った。
大島の指が、夏芽の肩から背中へとこぼれ落ちてゆく。力を入れて夏芽を抱きしめようにも、崩れ落ちていく指先は、あまりにも、あまりにも、もろかった。