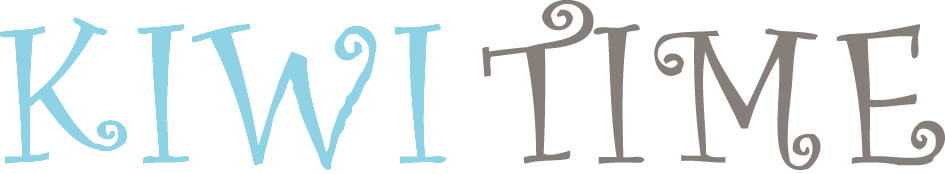「そろそろ起きなさい。学校に遅れるよ。もう二回目よ。」
優しい口調で伝えているつもりなのに、少し苛立った気持ちになってしまう。久美は卵のサンドイッチを作り終えてから、フルーツとスナックと共に至ってシンプルなお弁当を三人分用意している。一番上の長女はいつも時間通りに起き、一番下の次女は一回起こしに行くとすぐに起きてくる。
「起こしにいってきて、今日はテレビ見るのを無しにするよって。」
コーンフレークが入った小さなボールに刻んだバナナを入れている長女は、一旦手を止めて、真ん中の長男の部屋に向かった。リビングとキッチンが一緒になっている狭い部屋から足音をたてながら歩いて行く様子が伝わる。その足音をかき消すように、さらに大きな洗濯機が回っている振動音が聞こえてきた。
朝の七時半になると、機嫌悪そうな長男がようやく起きてきた。朝食、歯磨き、洗顔、着替え、学校の支度などを子供にさせるのにいつも忙しい。当てにならない天気予報をラジオで聞きながら、洗濯物を外で干すのか、部屋で干して乾かすのかを決めかねている。久美は、砂糖なしミルク入りのコーヒーを飲みながら朝食を急いで食べ、部屋着から仕事着に着替えた。そして、急いでうっすらとした化粧をしたころには、すでに八時を回っていた。仕事に行くのが嫌だと思う時間がないほど、あっという間に時が過ぎて行く。
子供と一緒に家を出ようと、騒がしい朝が一旦終わろうとした時に、家の電話が鳴っているのに気づいた。学校への見送りのために時間がない。
なんでこんな時に。電話に出ようかどうか一瞬迷った。突然、先ほどまでは寝ぼけていた長男が久美に言った。
「電話が鳴っているよ、でたほうがいいのじゃない。」
急いで玄関からリビングに戻り、留守番電話のメッセージが始まる直前に久美は電話にでることができた。朝早くから何なのだろう、忙しいのに。眉間にしわを寄せた険しい表情で苛立ちを隠せずにいた。
「ボーナス•ロトですが、久美さんでしょうか。」
声が高くて柔らかい口調の若そうな女性が丁寧にゆっくりと久美に伝える。
ボーナス•ロト、毎月積み立て形式で貯蓄する金融商品。抽選で小額から大金まで毎月当たる宝くじ的なボーナスが得られる。久美は毎月二十ドルを仕事の給料で入金された銀行口座から自動引き落とししていた。もう十年ぐらい積み立てをしていて数千ドルの積み立てまでに膨らんでいた。
「実は、今月のワン•ミリオン•ドルが久美さんに当たりました。」
百万ドルということは、1億円相当があたったということか。これまでの出来事が急に脳裏に蘇った。今までの子供の貧乏時代、一人暮らしでの質素な暮らし、そして結婚してからの再び貧乏生活。これが全て終わり、新たな裕福な生活が始まる。いや、そんなはずはない、これは悪徳商法の電話かもしれない。
「今日にでもこちらにお越し下さい、小切手をお渡しします。」
これは本当かもしれない。今すぐにでも行こう。子供を学校に送る事や、仕事に行く事を一切忘れていた。
執筆:20 歳の時に過ごした北島タウランガの思い出が忘れられない京都出身。大阪と東京に移り住み、カナダでスキー、オーストラリアをオートバイで一周した後、NZの銀行で10年間仕事をしながら短編小説5話を執筆(キィウィの法則、初めての出会い、私の居場所、10枚のチケット、魔法の子育て)。夢は日本で本を出版すること。
この記事はニュージーランドの日本語フリーペーパー「KIWI TIME Vol.96(2018年3月号)」に掲載されたものです。